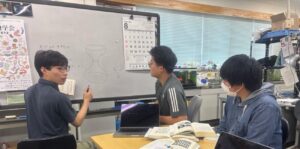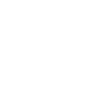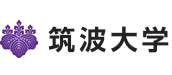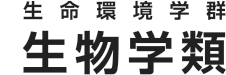生物学の古典を読む:「種の起源」を読んで
「たしかに、古代の祖先種は現生種の胚段階に類似しているとされる法則は正しいかもしれない。しかし、地質学のデータは、まだそれほど遠い過去までは明かしてくれない。したがってこの法則の証明には、まだまだ時間がかかりそうだし、永久に証明できないかもしれないということも、念頭に置いておくべきだろう。」(「種の起源」渡辺政隆訳、光文社文庫)
進化と発生の統合を掲げる進化発生学はHoxコードの発見に端を発する、比較的新しい学問分野として語られがちです。しかし19世紀に書かれた「種の起源」の第13章「生物の相互類縁、形態学、発生学、痕跡器官」にて、進化と発生に関する問題提起がすでになされています。なぜ分類において胚や幼生が重視されねばならないのか。なぜ特定のグループに属する生物の胚の形は互いによく似ているのか。当時の形態学が気づいていたこれらの観察事実に対して、ダーウィンは「変化を伴う由来」を反映するものとして説明を試みました。この試みでたどり着くのは、胚は共通の祖先形に由来するという、反復説的な見方です。一方でこの見方を否定する数々の例外にも直面します。非常に近い系統において幼生の形態がまるで異なる場合があること。近い系統で共有された胚構造や幼生を完全に失い、成体のような形態から直接発生してくる場合があること。これらの例外は反復説的な見方に異を唱えるものに他なりません。なにより、反復を証明するために必要な、進化の直接証拠たる化石記録はあまりにも不完全。それでもダーウィンは進化と発生のあいだにみる反復的な性質は事実でありうるとし、
「そのように胚発生の段階には、いくぶんか不明瞭なかたちではあるが、大きな動物綱それぞれの共通祖先の形態が反映されているという見方をすると、発生学に対する興味ががぜん高まることになる。」
と述べて発生学に関する記述を終えています。
状況は2024年になった今も大して変わりません。確かにここ数十年で進化発生学は分子生物学の発展と結びつき、ケーススタディを蓄積してきました。「由来」は「相同性」と読み替えられ、発生の類似は相同性の証左たりえるとする仮定をもとに、成体のかたちを見るだけでは気づけない進化を解き明かしてきたのは事実です。しかしこの営みは同時に例外も暴き出しました。祖先の遺伝子ネットワークを転用することで新たな形態を生むコ・オプションや、形態は変わらないにもかかわらず、それをもたらす発生機構だけが変化する発生システム浮動。階層間の繋がりを無視するかのごとく躍動する生物システムは、発生に由来を求めるわたしたちを笑います。進化と発生を結ぶそれっぽい「お話」をケーススタディでは持っていても、結局真の意味で進化と発生が結びついたことなどない。それでも、進化と発生のあいだになにか関係があるように思えてしまう。こうしてみると皮肉なことに、概念的な面で我々は今ダーウィンの時代を反復しているようです。生物の多様性と共通性という相反する特性を統一的に説明した自然選択のような枠組みが、進化と発生のあいだにも本当にあるのでしょうか。我々は今一度、遠い過去に立ち返る必要があるかもしれません。